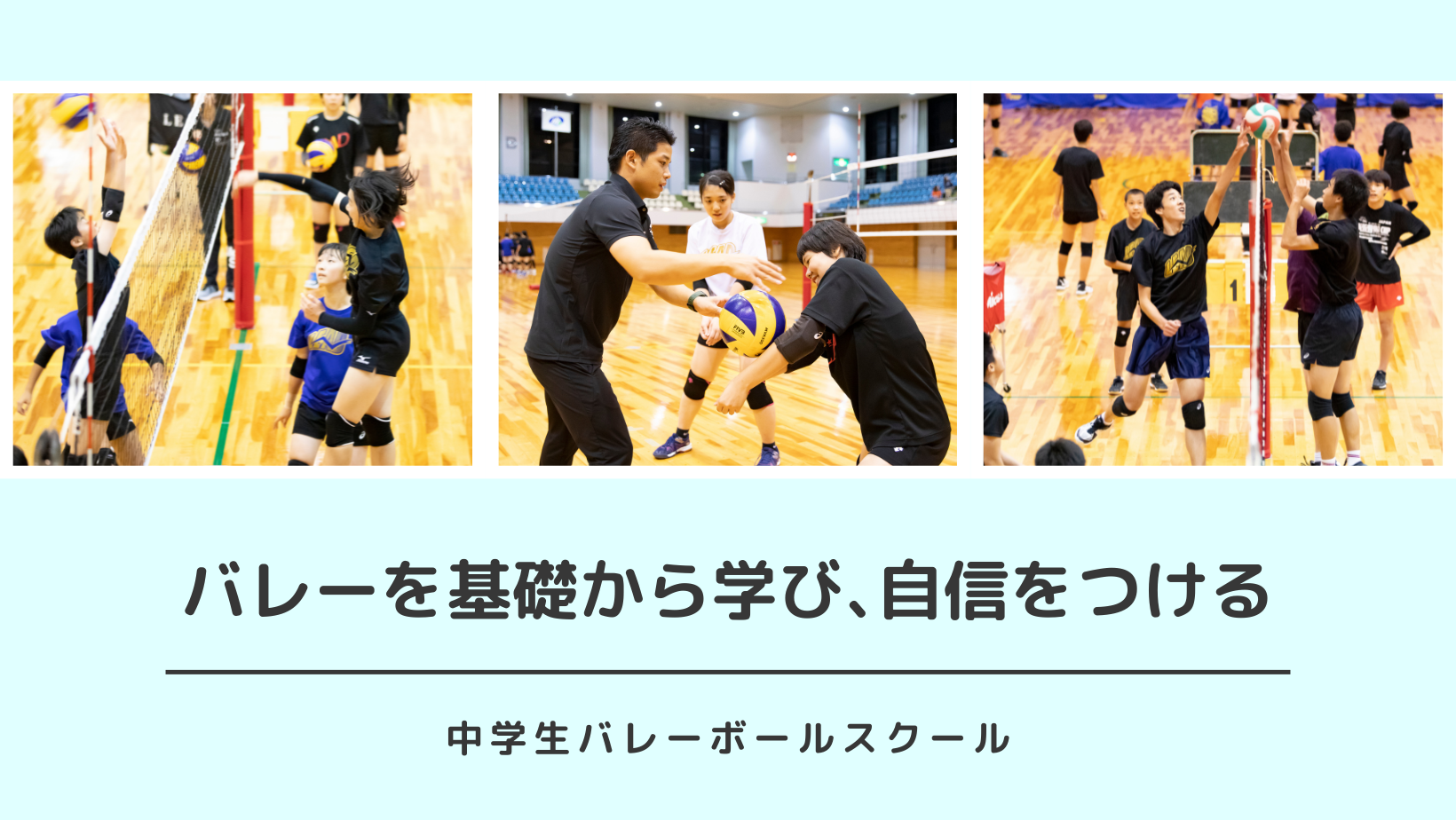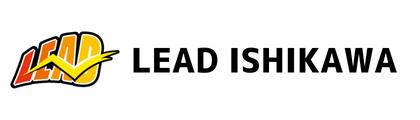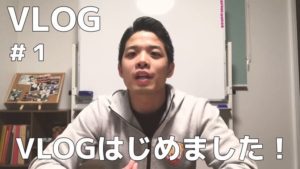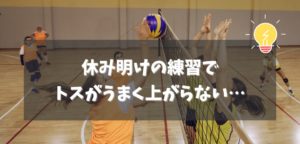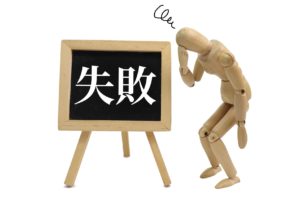石川県/LEAD/バレーボール教室/バレーボールスクール/幼児体育指導
前田幸介
あなたは、ディグをする際に「どこで守ればいいか分からない」ということはありませんか?
各チームで、ディグの基本ポジションやフォーメーションは必ず決められていると思いますが、
毎回同じポジションとは限らないことをご存じでしょうか?
たとえば、
- 相手のトスがネットから離れた時
- 相手のトスが短い時
- 相手のトスが長くアンテナよりも外の時
この3つは、試合中に何度も出てきますが、あなたならどのような行動にでますか?
相手のトスに合わせて、ポジショニングを変える?
それとも、決められた基本ポジションを守る?
この判断は非常に重要で、一つ間違えると失点に繋がることは言うまでもありません。
相手を見て判断する!
さて、先ほどの質問についてですが、
やはり「相手のトスに合わせて、ポジショニングを変える」必要があります。
また、トスだけで判断するのではなく、
さらに「相手アタッカーを見て判断する」必要があります。
目線の運び方としては、こうです!
- ボール
↓- セッター
↓- ボール(トス)
↓- アタッカー
これは、バレーボールの基本です。
相手のトスが離れているのであれば、
相手のできることは「長いコースの打ち分け」か「ハーフスパイク」に限られてきます。
そのため、
- 後衛のレフトバックは長いコースを想定し、ポジショニングを行う
- 前衛はハーフスパイクを想定し、ポジショニングを行う
もし、相手のトスやアタッカーの体勢を見ずに、いつも通りのポジションに構えていた場合、
そこにはボールは来ないため、失点に繋がる可能性が高くなります。
相手のトスが短い時は、
- バックセンターはストレートコースよりにポジショニングを行う
- ライトの後衛はブロック後ろのフェイントのケアに回る
トスが短いと、打てるコースがかなり限られてしまうので、
アタッカーは、ストレートの奥やブロック裏にフェイントをしたくなります。
ここで、フェイントを落としたり、ストレートの奥にきたボールがとれないと、
相手のディフェンスを崩した意味がありません。
自分で考えて行動する!
相手を見て判断する場面は、もっとたくさんあります。
ですが、
チームで決められたフォーメーションがあるから・・・
違うところにいると怒られるから・・・
といった理由で、適切な判断とポジショニングをできない選手がいます。
また、いつも指示をされる習慣がつきすぎて、自分で考えて行動することなく、
言われてから「あっ!」と気づく選手もいますね。
この2つは、あなたがバレーをする上で、ものすごくもったいないことです!
なぜなら、自分で考えてやってみるからこそ、バレーボールはおもしろいのです!
練習の時から「トスが◯◯だから、ここだな!」と動いてみる。
目線は「ボール・セッター・ボール・アタッカー」を意識する。
相手を見て気づいたことを「ストレート!」や「フェイント!」などと声を出してみる。
そうして実践することで、試合で自然と動けるようになっていきます!
もし間違えたら、次また改善してみればいいのです!
ぜひ今日から、練習で実践してみてはいかがでしょうか!
PS.バレーボールの基礎を楽しく学びたい人は、ぜひLEADのバレーボールスクールへ!
↓ ↓ ↓