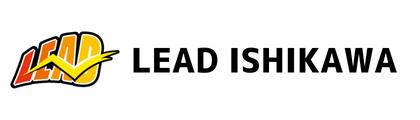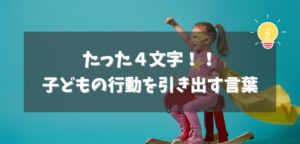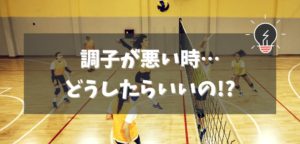石川県/バレーボールクラブ/バレーボールスクール/LEAD
前田幸介です。
ポジションの固定はしない
LEADのスクールではポジションの固定はしません。
もちろん現ポジションのスキルアップをメインに練習は行いますが、いろんなポジションを経験し、成功体験を重ねながら自分たちのプレーできるポジションを増やしていくことで、これからの可能性を広げていくことに繋がるからです。
身長の小さい選手が
- 部ではレフトなのでレフトがしたいです。
- リベロしかできないのでリベロをやります。
- セッターしかやったことがないので、スパイクはいいです。
身長が伸びるかもしれないし、伸びないかもしれない。
高校に行けばネットの高さも高くなります。
このような身体的な変化や環境の変化に対して、今後を想定して今のうちから新しいポジションを経験しスキルを磨いておけば、プレーの幅が広がりいろんなことに対応できる選手になります。
今にフォーカスし過ぎず、今後のあなたの可能性を信じよう!
新しいポジションに挑戦し、新たな目標や課題を見つけ真剣に取り組んでいくと、今よりももっとバレーが楽しく感じると思いますし、必ず上手くなります。
もし、新しい別のポジションも経験し、自分の可能性をさらに広げたいなどありましたら、LEADバレーボールスクールで一緒にやりましょう。
そういった選手もたくさんいるので、同じ思いをもった仲間にも出会えますよ!
それでは!
「もう、部活もバレーも辞めよう…」と悩んでいた子が、なぜ強豪校進学を決意するまでに成長したのか?
LEAD中学生バレーボールスクールの詳細はこちらからご覧ください。